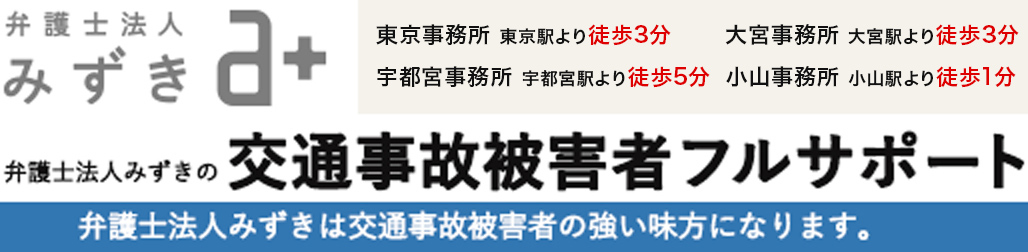~後遺障害は志望する仕事にどこまで影響を与えるか~【後遺障害8級相当】(名古屋地裁平成28年3月18日判決)
事案の概要
18歳の男子大学生Xのバイクが交差点を直進しようとしたところ、右折してきたY運転の乗用車に衝突され、第7・第8胸椎破裂骨折等の傷害を負ったため、XがYに対し損害賠償を求めた事案。
Xは脊柱の障害について、損保料率機構により、後遺障害等級8級に相当するものと認定された。
主な争点
後遺障害の逸失利益(労働能力喪失率と労働能力喪失期間)
主張及び認定
| 主張 | 認定 | |
|---|---|---|
| 物的損害 | 41万5480円 | 41万5480円 |
| 治療費 | 94万6175円 | 94万6175円 |
| 入院雑費 | 10万5000円 | 10万5000円 |
| 文書料 | 5400円 | 5400円 |
| 休業損害 | 36万2470円 | 22万5540円 |
| 後遺障害逸失利益 | 4685万0442円 | 2108万4233円 |
| 傷害慰謝料 | 250万円 | 211万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 870万円 | 830万円 |
| 過失相殺(25%) | ▲2489万3871円 | |
| 既払金 | ▲231万1253円 | ▲231万1253円 |
| 弁護士費用 | 574万1000円 | 200万円 |
| 合計 | 6331万4714円 | 2458万2618円 |
判断のポイント
①労働能力喪失率について
(1)裁判所の判断
Xは、残存した脊柱の変形の後遺障害により、45%の労働能力を喪失したと主張しましたが、裁判所は、喪失した労働能力は20%であると認定しました。
本件でXの労働能力喪失率を20%と認定した理由として、裁判所は、大学で建築を専攻しているXが、本件事故後も就学を継続しており、脊柱の変形障害により「将来の志望について変更を余儀なくされたなどという事情がないことからすれば、現時点においては脊柱の変形そのものによる労働能力の低下が顕在化しているということはなく、労働能力に影響し得るのはもっぱら変形した胸椎周辺の疼痛、すなわち局部の神経症状ということとなる。」として、Xの主張する45%までの喪失があるとは認められないと判断しました。
もっとも、脊柱の変形が、今後加齢によって新たな痛みを及ぼしたり変形の度合いが強まったりするおそれは多分にあることからすると、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の労働能力喪失率である14%では足りず、将来の悪化を見込んで11級の喪失率に相当する20%と認定しました。
(2)コメント
後遺障害別等級表上の8級の労働能力喪失率の基準値は、Xの主張するように、45%とされています。そのため、単純に考えればXの主張は正当なものとして認められるべきものとも思えます。しかし、この基準値は後遺障害の種類や程度によっては、実際にどのくらいの労働能力が喪失しているかを測定するのは困難であるために、あくまでも目安としている基準であって、基準値どおりの喪失率で相手に逸失利益を請求しても、裁判では、被害者の職業や後遺障害の程度等を考慮して、現実にどの程度仕事に影響を及ぼしているのかが厳密に判断されることになります。
本件では、Xが大学生であったために、裁判所は、将来の就職について、後遺障害が影響を及ぼしうるのかどうか、という点を重視し、Xには志望を変更せざるを得ないような事情がないことを考慮して、裁判の時点では、8級の基準値相当の影響は認められず、局部の神経症状による影響にとどまると判断したところがポイントになります。もし脊柱の変形障害によって、Xが就職活動をすることができなくなったり、志望する仕事に就けても継続することができなくなってしまうような事情があったのであれば、基準値どおりの喪失率が認定される可能性があったのかもしれません(もちろん、志望どおりの仕事に就けるのが一番だと思いますが)。
また、本件のもう1つのポイントは、裁判所が、Xに生じている労働能力の喪失は局部の(頑固な)神経症状による、と判断しながらも、単純に12級の喪失率14%とするのではなく、1等級上の11級の喪失率20%を認定したところにもあります。裁判所も、体幹の中心を支える脊柱の恒久的な変形という重大な障害で、加齢による今後の痛みや変形の悪化が生じる可能性があるということを考えて、通常の12級13号の喪失率の基準値で考えるべきではないと判断したのです。このようなところにも、裁判所が事案の実態に即して、バランスを考えながら判断していることが窺われます。
②労働能力喪失期間
(1)裁判所の判断
労働能力喪失期間について、Xは症状固定時の20歳から就労可能年齢の67歳までの47年間であると主張したのに対し、Yは10年程度であると主張しましたが、裁判所は、Xの主張どおり47年間と認めました。
Yは、Xの骨癒合がきちんと得られているため、今後筋力の回復や症状に対する慣れが期待できることを、喪失期間を10年程度とすべきとする理由として主張しましたが、裁判所は、脊柱の変形は生涯戻ることはなく、かえって症状が悪化する見込みもあることから、Yの主張のような期待をすることができる根拠はない、としてその主張を退けました。
(2)コメント
本来後遺障害は、基本的にそれが生涯残ってしまうものを指すため、労働能力喪失期間は、人が通常働けると考えられる期間、すなわち就労可能年齢までとされるはずですが、いわゆるむち打ち症で神経症状が後遺障害として認定される場合、時間が経つにつれて症状に対する慣れが出てくるとして、労働能力喪失期間は12級13号では10年程度、14級9号では5年程度と認定される例が多いです。もっとも、裁判では後遺障害の具体的な症状に応じて喪失期間が認定されますので、むち打ち症であっても、上記の期間よりも長期、もしくは就労可能年齢までの喪失期間が認められた裁判例も存在します。
今後正常な状態まで回復するとは考えにくい脊柱の変形障害については、変形が原因で引き起こされる疼痛などの症状も生涯継続すると考えられます。しかも、高齢になると、脊柱は後弯するようになる場合もあり、そのような加齢性変化と後遺障害の変形が相まって、痛みが増加したり、変形の度合いが強くなったりする可能性があることは、十分予測できます。本件では、裁判所が、そのような脊柱の特性や将来予測も考慮して、通常のむち打ち症のような症状に対する慣れが出てくることが期待できないとして、Yの主張を採用せず、就労可能年齢までを労働能力喪失期間を認めたところがポイントです。
後遺障害の逸失利益の算出は、現在の、または将来就くであろう仕事に、どの程度の就労制限が、どのくらいの期間に渡って生じるのか、という将来予測を伴うため、示談交渉や裁判で適正な逸失利益が認められるには、具体的事情やその算出根拠をしっかりと主張立証することが重要です。後遺障害が認定されたものの、相手の提示する示談金額に納得できない、適正な金額なのかわからない、というような場合、まずは弁護士にご相談ください。